ここで謡われるのが〈海人〉の「玉ノ段」です。
能〈海人〉では、母の供養のために故郷を訪れた房前の大臣の前に、母の亡霊が現れ、玉取りの様子を物語ります。その中心的な見せ場で、地謡に合わせて舞います。
讃岐の国志度の浦の地で、龍神に盗られて竜宮城に持ち去られた宝珠を取り戻すために、短刀一本を手に、命綱を腰に巻いただけで海底深く潜った、海人の物語です。
「玉ノ段」は『申楽談儀』にも記されている古い仕舞だということは先回お示ししました。どのようにして海底の竜宮城に行き、どのように宝珠を盗み出し、逃げ出して海上まで浮かび上がれたのかということを表現した面白い見せ場です。当て振り的に動くだけでも、見応えのある舞になってしまう、ワクワクする内容で、現代でも謡も舞も人気のある演目です。 そのような名曲を、寝て謡う、笑いの対象にしてしまう、こういうところが狂言の狂言らしさなのでしょう。
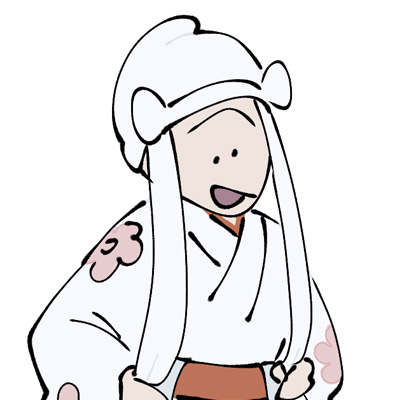
「玉ノ段」については、第5回で詳しくお話しします。

「玉ノ段」はかなり長い謡で、前半は海に飛び込んで海底まで行き、恐ろしさに立ちすくむ様子、故郷と愛する人達を思って涙する様子などが丁寧に描かれています。この部分は心情表現などが中心で、あまり目立った所作はありません。
そこを利用して、寝たまま謡う太郎冠者を不信に思った主人が、身体を持ち上げてみるという動作を繰り返し行います。

最初のうちは寝ていると声が出、起きては声が出ないと対応していますが、ふとしたことでそれが逆になってしまい、寝ていて声が出ず、起きると朗々と謡うようになります。
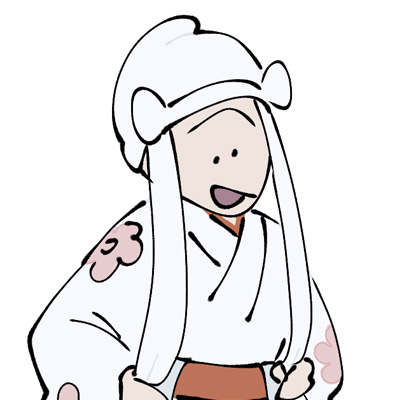
声が出る出ないの変化をスムーズに一続きの謡の中で謡い分けるので、いっそう面白みが増します。
主人はいつから太郎冠者の策略に気づいたのでしょう。起きて声がでるとなったときのあきれ顔、あるいは怒り? どのような反応をしているのか、太郎冠者の演技に注目するのはもちろんですが、主人の反応の仕方も見ものです。

不安や哀しみを断ち切って決意を新たに、志度寺の観音に祈りを献げる場面から、太郎冠者は立って舞い始めます。
ゆったりした謡がここから変わります。激しくたたみかけるような戦闘シーンを思わせる謡い方です。
